多品種少量栽培から経営を転換、規模拡大へ
近藤さんは現在、40歳。大学を卒業して会社に1年勤めた後、農業分野で国際協力の仕事をしようと茨城県の専門学校に入学。野菜の栽培方法を学んでいるとき、同じ学校にいた妻の美保子(みほこ)さんと知り合った。
美保子さんの実家は瑞穂町の野菜農家。近藤さんは専門学校を出るとき、計画通り海外に行こうと思っていた。だが美保子さんの家族から「忙しいのでしばらく手伝ってほしい」と頼まれ、海外に行くのを先送りにした。
もともと農業に関しては「もうからない」といったイメージしかなく、職業の選択肢に入れていなかった。だが畑に出ているうち、「農業も面白いかもしれない」と気持ちが変化。そのまま美保子さんの実家で就農した。

農業に面白さを見いだした近藤剛さん
近藤さんが働き手に加わったころ、美保子さんの実家は0.6ヘクタールほどの畑で、約30品目の野菜を作っていた。都市近郊の農業でよくある多品種少量栽培。地方の産地が大勢の農家で特定の品目を効率的に作るのと比べ、ニッチな需要を狙った営農のあり方だ。売り先は地元の直売所だった。
幸運だったのは、近藤さんが非農家の出身だったにもかかわらず、美保子さんの父親が自分のやり方を押しつけようとしなかった点だ。30代前半のころには、自然と近藤さんが経営全体を切り盛りするようになっていた。
その結果、販売と栽培の両面で営農のかたちが大きく変化した。売り先は、都内各地のスーパーや小中学校向けの給食センターなどに広がっていった。地域の農業の担い手として認められるようになったからだ。一方で、大口の売り先の要望に応える過程で、品目数はどんどん減っていった。
近藤ファームはいま栽培面積が5ヘクタール。5年後には10ヘクタールに拡大すると見込んでいる。栽培しているのはコマツナやネギなど6品目。いずれ就農時の10分の1の3品目まで絞り込もうと考えている。

近藤ファームの畑
品目を統一する合理的な理由
「就農したときから家族経営ではなく、組織的に農業をやりたいと思っていた」。近藤さんはそう語る。現在、3人の社員と6人のアルバイトが働いており、社員は完全週休2日制。働きやすい環境づくりを心がけている。
近藤さんは「農業が楽しいと思ったので就農した」と話すが、それは栽培というより、経営を通して得られるものだった。その延長でいま目標に掲げているのが、瑞穂町を中心に農家の仲間を集め、産地をつくることだ。
品目を絞り込んだのは、売り先の要望に応えながら効率を向上させる狙いもあったが、理由はそれだけではない。西多摩地区をはじめとして都内には農地がそれなりにある。だが各農家がバラバラに営農していることが多く、地域の特産品としてイメージが定着している農産物はほとんどない。
近藤さんは品目を絞ることで、こうした状況を打破できると考えている。各農家が自分の作りたいものだけを作るのと違い、品目を統一すれば「栽培技術や機械を農家の間で共有しやすい」からだ。「うちだけで大きくなるのではなく、みんながいい思いをできる産地をつくりたい」と強調する。
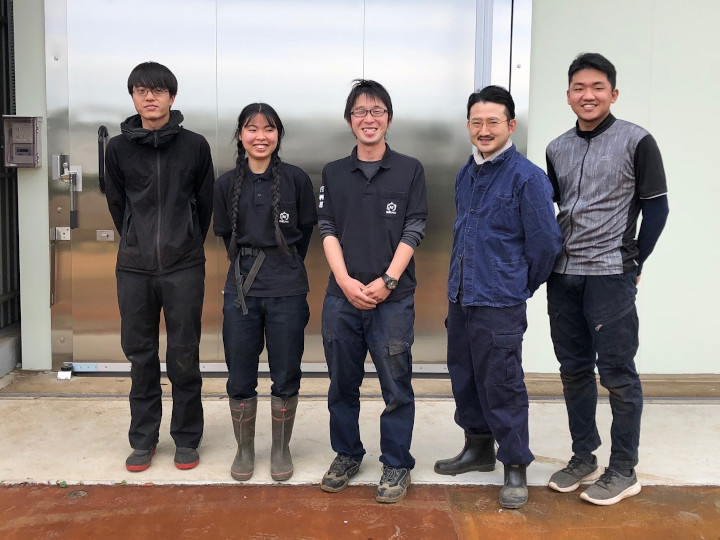
近藤ファームのメンバーたち
これから力を入れようと思う3つの品目は、そうした展望を踏まえて選んだ。ネギは作業の多くが機械化されており、他の農家と組んで効率化しやすい。コマツナは鮮度が品質を左右するため、都市近郊の強みを発揮できる。
とくに戦略作物とにらんでいるのが、サツマイモだ。焼き芋や大学芋など加工の用途がさまざまにあり、営農の特徴を出しやすいのが強みの一つ。地元の子どもたちを対象に芋掘り体験のイベントなどを開けば、食育に貢献することもできる。それが、産地としての魅力を高めることにつながると考える。
学校との連携はすでに一部で進みつつある。地元の農業高校の生徒を学校公認でアルバイトとして受け入れているほか、この学校の食育のカリキュラムに近藤ファームでの栽培体験を組み込む方向で話を進めている。
近藤ファームが給食に食材を提供している学校は都内に100以上あり、食育への協力を通して東京の農業の存在感を高める余地は十分にある。近藤さんは「東京都に住む人たちと一緒に産地を育てていきたい」と話す。

サツマイモ畑にマルチを敷く
戦略づくりを支える担当を配置
一連の話は、近藤さんの頭の中だけの構想と思う人もいるかもしれない。そこで、実現に向けて動き始めていることを組織面から示しておきたい。
もし規模拡大への対応に追われ、近藤さんが栽培現場にとどまっていたら、構想の実現はおぼつかないだろう。外部の人と接する時間をとれないからだ。そのために近藤さんは畑を離れ、マネジメントに専念することにした。
しかも最近、それをサポートするためのスタッフも置いた。6年前から働いている工藤正明(くどう・まさあき)さんだ。農場が目指す方向を具体的な言葉に落とし込んで資料を作成したり、外部に発信したりするのが仕事。営業も受け持つ。この取材でも、幾度か近藤さんの言葉を補完してくれた。

戦略づくりで近藤さんを支える工藤正明さん(右)
かつてと比べ、農業はずいぶん変わったように思う。農業をポジティブな仕事と考える若者が増え、企業的な経営が続々と誕生し、都市近郊の農業も注目を集めるようになった。そうした中で、近藤さんのように東京で新たな産地づくりを目指す人が登場したことも、時代の変化を映しているだろう。
近藤さんは「東京の野菜の需要を、地方の生産でまかなっていることにもどかしさを感じていた。もっと頑張れば都内の農地で需要に応え、農業を活性化させることができる」と話す。常識を破る挑戦が始まりつつある。































