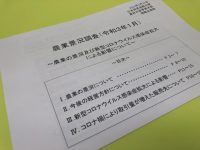農水省の目標は事実上、EUの追随
有機農業の面積を大幅に増やす目標を、農水省は「みどりの食料システム戦略」という政策指針の中で掲げた。背景にあるのは地球環境問題への国内外での関心の高まりで、指針は農薬と化学肥料の削減に重点を置いた。
農薬は生態系を損なう可能性があり、窒素肥料を化学合成する際には化石燃料を使う。農薬と化学肥料を原則として使わない有機農業を推進するのは、生物多様性の確保や脱炭素の流れに即しているように見える。
とくに意識したと思われるのが、欧州連合(EU)の動向だ。EUは2020年に出した「ファーム to フォーク戦略」で、有機農業の比率を10年間で25%に高める目標を打ち出した。農水省の目標は事実上、その追随だ。

有機農業を25%に高める目標を掲げた農水省
指針は日本の農業が直面する問題として、人手不足や気候変動なども挙げている。そうした課題に生産者が対処するには、作業の効率化を可能にする農薬や化学肥料の使用はむしろ有効な手段とみることもできる。
その点を踏まえ、指針は後押しする対象を有機農業に限定せず、日本の農業全体で化学肥料や農薬の使用量を減らすことも提起している。有機と違い、「ゼロ」ではなく「削減」を目指すというのは現実的な選択肢だろう。
そこで考えるべきは、有機農業を25%にするという目標の妥当性だ。欧州と比べると、日本は有機農業が普及しておらず、耕地に占める比率は1%に満たない。農家や研究者が努力を怠ってきたからではない。雑草や病害虫が発生しやすい日本の気候が、有機農業にとって大きな壁になっているからだ。
有機農業を25%に高めるのは可能なのか、三つの例から見えてきたこと
25%は達成可能なのか。それを考えるため、現状を点検してみよう。手がかりにするのは、この連載で取り上げてきた生産者たちだ。

稲作で有機栽培に取り組む大野満雄さん
まずは稲作から。大野満雄(おおの・みつお)さんが代表を務める農業法人、東町自然有機農法(茨城県稲敷市)は名前の通り、有機に力を入れている。40ヘクタール弱の栽培面積のうち、8ヘクタールを有機が占める。
有機を長年続ける中で、つねに課題になってきたのが雑草対策だ。機械で除草するほか、効果があるとされる方法をいくつも試してきた。水田にコメぬかをまいたり、水を深くしたり、紙のシートを敷いたりしてみた。
その一つ一つをふり返りながら、大野さんは「効くときと、効かないときがある」と話す。出した結論は雑草との共生。できるだけ取り除くが、ゼロにすることまでは目指さない。その分、収量に影響は出るが、「雑草も脈々と生きてきた。そこには何らかの意味がある」と考えるようになった。

伏田直弘さんは葉物野菜で規模拡大してきた
茨城県つくば市の野菜農家、伏田直弘(ふしだ・なおひろ)さんはさまざまな葉物野菜を有機で栽培している。運営しているハウスは約50棟あり、売り上げはもうすぐ1億円に届く。有機農家としては大規模の部類に入るだろう。伏田さんは「有機栽培は簡単で、しかももうかる」と強調する。
最大のポイントは、有機でも作りやすい品目に絞ってきたことにある。2015年に最初のハウスを建てて農業を始めたときは、試しにカブも育ててみた。だがアブラムシが発生して全滅したため、すぐに作るのをやめた。
一方、コマツナやミズナなどの葉物野菜は苗を植えてから収穫までの期間が短いため、仮に病害虫が発生しても、植え替えて栽培をリセットすることができる。葉物野菜に絞って規模を拡大してきたのはそのためだ。
次の目標は、あえて有機では作りにくい作物を作ること。ハードルが高いほど、うまくいけば他の農家と差を出しやすいからだ。これまでトマトやナスを育ててみたが、虫が発生したので中止した。2021年はイチゴに挑戦する。伏田さんにとっても、品目を増やすのは道半ばのテーマなのだ。
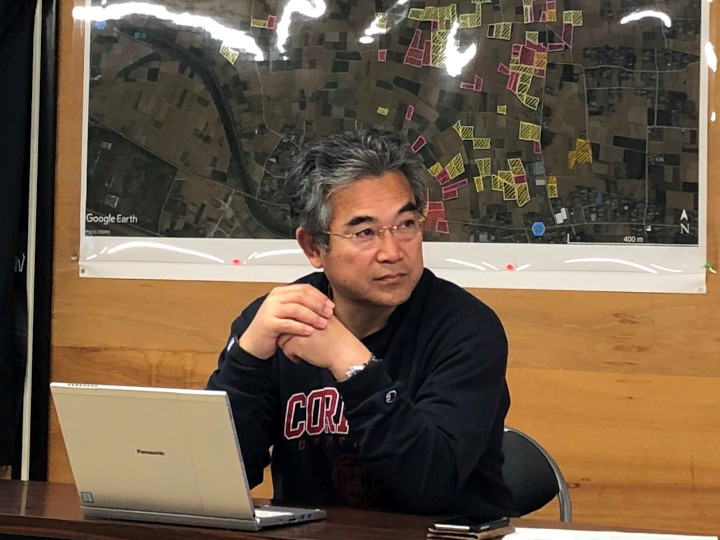
大手食品メーカーとの差別化を目指す沢浦彰治さん
野菜くらぶ(群馬県利根郡昭和村)を経営する沢浦彰治(さわうら・しょうじ)さんも、有機栽培を始めることで事業の拡大にはずみをつけた。30年近く前、農産物の宅配会社から無農薬栽培を求められたことがきっかけだ。
有機で付加価値を高めるのは、いまも経営戦略の柱の一つ。例えば、6次産業化の一環として取り組んでいるコンニャクの製造は、原料となる芋の栽培から加工まで、国が定めるJAS有機の認証基準をクリアしている。
戦略には二つのポイントがある。まず職人にしか作れないような高級品の開発は、市場が小さすぎるので目標にしない。一方で大量生産が可能な商品は大手食品メーカーとの競合に巻き込まれるため、これも開発のターゲットにしない。そこで独自性を出すための武器にしたのが、有機栽培だった。
ここで三つの例を取り上げたのは、いずれも規模が平均を大きく超えているからだ。田畑の隅々まで目が行き届く零細経営なら、有機栽培をずっとやりやすいが、それでは広がりを欠く。そして三つの例から見えてきたのは、栽培品目の多様化や生産量の拡大には一定の制約があるという点だ。
有機農業の推進は無視できない流れに
日本での有機農業は、最近になって突然始まった取り組みではなく、約半世紀の歴史がある。茨城県土浦市の有機農家、久松達央(ひさまつ・たつおう)さんは「それでも画期的に面積を拡大できる技術はまだない」と話す。
マルチなどの農業資材や農業機械を含め、有機に役立つ技術を積極的に取り入れてきた。農業・食品産業技術総合研究機構の研究者とも連携してきた。それを踏まえ、農薬なしで効率を高めるのがいかに難しいかを力説する。
そんな久松さんにとって、25%という目標はあまりにも根拠が薄いと映る。だから「まずどこでどんな作物を育てれば、有機農業が可能かを整理する必要がある」と指摘する。だが、それでも目標の達成には懐疑的だ。

久松達央さんは有機農業の新技術を追求してきた
総括に移ろう。見えてきたのは、有機の面積を抜本的に増やすことの難しさだ。稲作の大野さんの場合は面積の2割を有機が占めるものの、収量の減少も伴った。収量を維持しながら面積を広げるのは簡単なことではない。
一方で、有機農業を推進するという国の方針そのものに意味がないと考えるのも早計だと思う。これまで有機農業が農政の優先課題になることはなかった。では国が本気で技術革新を後押ししたら、どこまで有機を広めることができるのか。追求してみる価値は十分にあるテーマだろう。

中国天津市のショッピングモールの食品売り場。「有机」は有機の意味
国際情勢にも目配りが必要だ。欧州が有機農業の推進で主導権を握ろうとしているほか、中国なども普及に積極的。食の安全や環境問題にどこまで資するかという議論とは別に、有機の推進は無視できない流れになりつつある。その中で、日本がどこまで何ができるかを考えるのは当然のことだろう。
25%という目標の是非をいったん脇に置けば、農水省に求められるのは、農薬や化学肥料の使用を減らすための詳細なシナリオを示すことだ。
「みどりの食料システム戦略」はスマート農業の活用などを挙げているが、誰が責任を持っていつまでに何を実現するのか。そうした技術で、営農のコストは本当に下がるのか。もし十分に下がらないなら、その分は補助金で支援するのか。消費者はそれに理解を示し、有機食品を受け入れるのか。
詰めるべきテーマはいくつもある。農水省は目標を掲げた以上、農家を含めた関係者が納得できるような具体像を示してほしい。それが見えてくれば、生産者は政策にそって営農のカジを切るべきかどうかを判断できる。