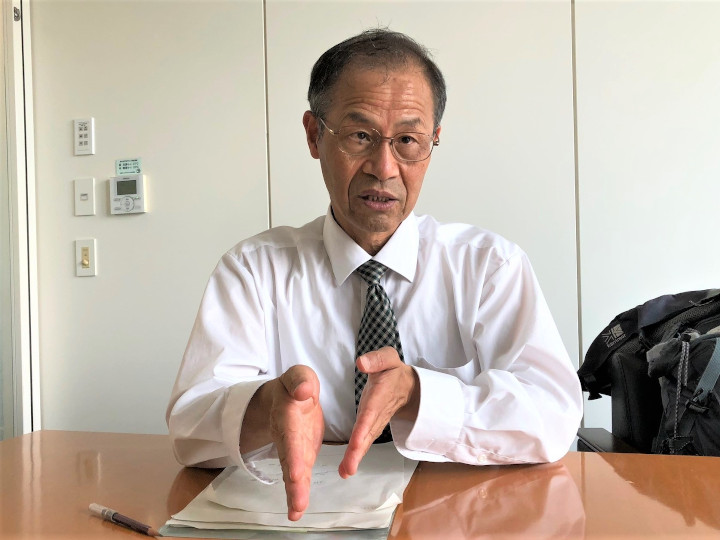コメには潜在的な需給ギャップがある
荒幡さんは1978年に農林省(現農林水産省)に入省し、稲作やコメ流通、農地などを担当した後、96年に岐阜大学の助教授に就任。同教授を経て、2022年度に筑波学院大学の教授に就いた。米国のトウモロコシ地帯「コーンベルト」にある米イリノイ大学の在外研究員も経験している。
一貫して稲作の実情やコメ政策を研究しており、「米生産調整の経済分析」(農林統計出版)、「減反40年と日本の水田農業」(同)、「減反廃止」(日本経済新聞出版本部)などの著書がある。内容は全国各地の調査をもとに詳細を究めており、文献や資料の分析だけでは得られない説得力がある。
ではインタビューの中身に入ろう。
──2018年のいわゆる「減反廃止」をどう評価していますか。
国が50年近く実施してきた減反制度は廃止になり、各県が自主的に主食米の需給を調整する形に変わりました。これは制度的には大きな変化です。ただ県から市町村へ、さらに各生産者に生産量が提示されており、実態はあまり変わっていないという見方もできます。
制度改正を円滑にうまくやったと見ることもできるし、反対に「内容が生ぬるくてとても改革とは言えない」と考えることもできるでしょう。
──制度を変えた後も補助金を使って飼料米の生産を奨励し、主食米の生産を抑制しています。
ご指摘の通り、飼料米の補助金がかなり効いています。その結果、現場で大きな混乱が起きるのを防ぐことができました。
大事なのは、コメの潜在的な生産能力と需要の間にギャップがあり、何か手を打たないといけないという点です。生産能力のほうが明らかに多いのです。減反を廃止しても、この状況で増産を推奨できるわけがありません。
極端な言い方をすれば、「市場原理に任せて、農家にコメを作りたいだけ作らせればいい。そうすれば、米価が暴落してコメを作らなくなる」と考えることもできます。でもそんな乱暴なことをすべきではありません。
どの程度の強さでやるかは別として、政策的に何らかの誘導が必要です。それを放棄して市場に任せるのは、農政の責任放棄です。

稲作は岐路に立っている
大豆やトウモロコシには増産の余地がある
──飼料米の補助金が手厚いため、主食米の値段の下落が心配な農家の多くは飼料米を選んでいます。その結果、小麦や大豆、飼料用トウモロコシなど輸入に依存している作物の生産振興が中途半端になっています。
それはあると思います。腰まで水につかって田植えをしなければならないような湿田地帯は、コメをつくる以外には選択肢がありません。そういう地域で飼料米を生産するのはそれなりに意義があります。
ところが実態は、火山灰土で水はけがよく、湿田はほとんどないような地域でも飼料米を盛んにつくっています。本来はいくらでも麦をつくれる地域にもかかわらずです。これは農家のせいではなく、政策に問題があるのです。農家は補助金を見て、経済合理性にもとづいて行動しています。
世界の飼料作物の単位面積当たりの収量はどんどん向上しています。それと比べると、日本の飼料用米の単収はあまりにも少ない。日本が置いて行かれないようにするためには、飼料米の補助金を出す際の基準収量を引き上げて、もっと収量を増やすように促すことが必要です。
たとえ補助金の支給基準を厳しくしても、湿田の多い場所はほかに選択肢がないので飼料米をつくり続けるでしょう。一方、そうでない地域はトウモロコシや大豆などをがんがんつくっていけばいいのです。
──トウモロコシや大豆などを拡大する余地はあるでしょうか。
米国のコーンベルトとは生産条件が全然違うので、とても太刀打ちできないという意見をよく聞きます。実際、イリノイ州でトウモロコシと大豆を栽培している畑の区画は1枚で32ヘクタールもあります。
ところが現地をジョギングしていて気づいたのですが、