これからの農業を担う若手に関心の高い「農薬講習」 どう充実させるべきか
長野県南部、南と中央の2つのアルプスの間に広がる上伊那地域では、水稲、野菜、果樹など様々な農業が営まれ、地域のこれからを担う新規就農者の育成支援に力を入れています。

その一つが、上伊那農業農村支援センターがJA上伊那と共同で毎年行っている「新規就農実践塾」です。新規就農者と就農研修生を対象に、基礎コース、野菜コース、果樹コース(りんご・ぶどう隔年)があり、基礎コース全6回のうち1回を農薬講習にあてています。
「昨年の実践塾でも農薬についての質問が多く、関心の高さがわかりました。一方、まだ実際に農薬を使ったことがない方もいる中で、講習でどこまで伝えられたのか不安がありました」と話すのは、同センターの黒澤窓(くろさわ まど)さんです。
昨年から「新規就農実践塾」の企画・運営を担当し、昨年度の農薬講習は自身がレクチャーしました。

長野県上伊那地域振興局 上伊那農業農村支援センター 技術経営普及課 黒澤窓主任
しかし、今年度は農薬講習を外部の専門講師に依頼することを決めました。
その理由として「農薬の取り扱いには注意が必要です。農薬の取り扱いについては、私が伝えるよりも外部の講師の方にお話しいただいたほうが、受講者が緊張感を持てると思いました」と話してくれました。
また、プロの講師から講習を受ける機会は、黒澤さんはじめ職員にとっても多くはありません。自らの勉強にもなると考えたそうです。
自治体や参加者の状況に合わせた講義 2,3か月ほどでスムーズに実施へ
クロップライフジャパンでは、農業関係者へ農薬の正しい情報を提供し、その適正使用に向けた正しい知識の普及活動を行っています。その一環として力を入れているのが、講師派遣事業です。
公益社団法人緑の安全推進協会に委託して、自治体、JA、直売所などで年間約200件の農薬講習を無償で行っています。
そのことをパンフレットの回覧で知った黒澤さん。問い合わせのメールをすると、すぐに緑の安全推進協会からOKの電話がありました。「無償でプロの講師が来てくれるならぜひお願いしたい」と、プログラムに組み入れることが決まりました。

問い合わせをしたのが4月末。その後正式に依頼し、受講者について新規就農者と就農研修生が半々であることなどの状況を協会側に伝えると、6月上旬に研修で使用する資料が送られてきました。
「参加される方の現状に合った内容だったので安心しました」と黒澤さん。6月末の講習に向けてスムーズに企画が進みました。他の業務もある中で、講習の資料を更新したり講義の準備をしたりする時間との戦いからも少し解放されたようです。
「新規就農実践塾」は、長野県のホームページやJA上伊那の広報誌などで募集告知しますが、黒澤さんら担当職員が新規就農者と就農研修生の一人ひとりに通知文の郵送やメールで参加を呼びかけています。
こうして、今年も塾生として十数名が集まりました。
参加者も満足、地域の担い手に刺さる農薬講習会
6月末、県伊那合同庁舎で行われた第2回目の新規就農実践塾で、緑の安全推進協会委嘱講師が「農薬の適正使用について」講習を行いました。同協会は全国に50人の専門講師を擁し、受講者や目的に合わせた講習を提供しています。

【左】講習会の様子 【右】緑の安全推進協会委嘱講師の出崎里永子さん
今回のトピックは、農薬の役割と定義、使い方と作用の仕方、リスクと安全確保、適正使用、事故防止。
資料やスライドを用いて、要所で質問を投げかけながらテンポよく進められ、受講者はメモを取りながら講師の話に集中していました。最後にマスクの正しい着け方の練習で約1時間半の講習が終了。質疑応答にも手が挙がり、講師が専門家としてスムーズに回答していました。
熱心に質問していた受講者2人に講習の感想を聞いてみましょう。
義父母のりんご園を手伝っていた宮﨑未来(みやざき みらい)さんは、2年ほど前から自身が栽培管理を主に担当することになりました。地区では共同防除をしており、当番が回ってくると会社勤めの夫が出てくれていますが、この機会に農薬を正しく扱えるようになりたいとの思いで講習に臨みました。

贈答用のフジなど40aの圃場でりんごを栽培している宮﨑未来さん
「農薬を使わないとリンゴの収穫は1割になると聞き、他の作物と比べて飛びぬけて低いことが衝撃的でした」と、自分ごととしてスイッチが入ったようです。
昨冬、伊那市に家族4人で移住した鹿島健太(かしま けんた)さんは、農業経営者を目指して来年からりんご農家での2年間の研修をスタートさせます。実は農薬メーカーの研究員から転職した異色の研修生。農薬を使う側として、法律違反をしないようにルールを再確認して安全に使うための注意点を学ぼうと講習に参加しました。
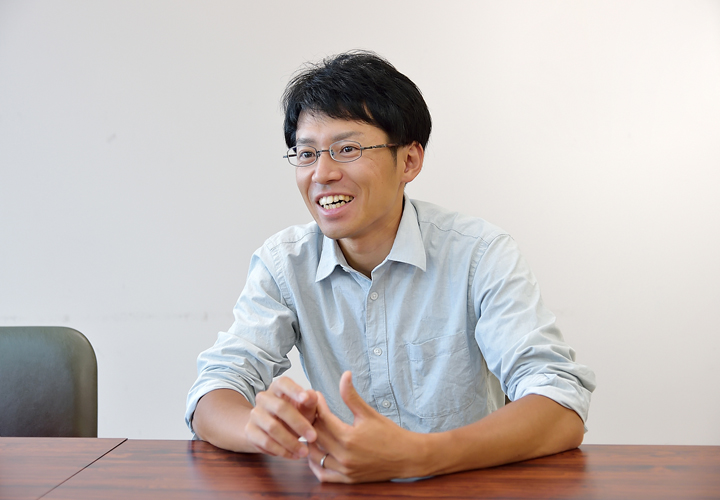
出身は大阪府ですが、趣味の登山がきっかけで、自然豊かな上伊那での移住就農を決めた鹿島健太さん
「使用農薬を間違えやすい作物の話で、トマトとミニトマトは別の作物として区別していることなどは改めて気を付けなければいけないなと思いました」と再確認できた点が多かったようすです。
2人が最も印象に残ったと言うのは、マスクの正しい着け方の練習。これは、昨年度の講習では行っていない内容のひとつです。
「マスクを隙間なく顔に密着させるコツがわかりました」と鹿島さん。就農したら正しい知識で農薬を選定し、環境負荷や防除コストの削減につなげたいと意欲的です。
「農業を続けていくために自身の防護は最も気を付けたいこと」と宮﨑さん。農薬を適正に使って消費者によいりんごを提供し、規格外のりんごで焼菓子などの加工品も作りたいと話してくれました。

正しいマスクのつけ方は意外と知る機会がない
新たな担い手の育成と自治体の負担軽減へ 農薬に関する悩みに応えるクロップライフジャパン
今回の講習会の成果を黒澤さんに尋ねると、「農薬取締法の目的について農薬事故の事例を挙げてお話しいただき、難しい話が具体的に伝わったように思います」と手応えを感じたようす。

受講者を見守る黒澤さん
「農薬は登録時に使用方法が定められており、ラベルに従って使用すれば健康影響がないようリスク管理されていること、このため適正使用が大事なことが理解できたのではないでしょうか。私自身もいろいろな場面で農薬について話す機会があるので、伝え方の参考にもなりました」と黒澤さん。
マスクの着け方など自身では指導が行き届きにくいところに関しても、外部の専門講師に丁寧に教えてもらうことで安全意識が高まったと感じて見ています。
地域の農業者からの農薬についての問い合わせにも、クロップライフジャパンのDVDや動画、リーフレット、ホームページ等を活用しているという黒澤さん。
「農業を始めた、あるいはこれから始められる皆さんが地域農業の担い手として活躍できるように、また、農薬の知識を身に着けることで消費者と自分の身、そして作物を守るお手伝いができたらと思います。そして講習を通して横のつながりを育んでいただけるといいです」と思いを語ってくれました。

クロップライフジャパンの講師派遣事業が、新たな担い手の育成と自治体の負担軽減につながることが実感できました。
関心のある自治体やJAなどの担当者さんは、以下のお問い合わせよりご連絡ください。
【取材協力】
長野県上伊那地域振興局 上伊那農業農村支援センター
【お問い合わせ先】
クロップライフジャパン
東京都中央区日本橋茅場町2丁目3-6 茅場町偕成ビル
公益社団法人 緑の安全推進協会
東京都千代田区内神田二丁目12-1






























