薬膳の世界から見たキャベツ

キャベツは別名タマナ、ボタンナと呼ばれ、漢名は甘藍(カンラン)と言います。薬膳の世界でキャベツは、五気は平、五味は甘に分類される食べ物です。
ヨーロッパ原産で、日本には18世紀の初めごろにオランダ人によって長崎に伝えられたと言われています。キャベツの魅力は何と言っても、煮ても焼いても生でも炒めてもおいしいという点。いろんな料理に取り入れて、摂取するようにすると体がどんどん整っていきます。虚弱体質の子どもには、キャベツのスープを作っておいて飲ませるのが効果的です。

キャベツの特筆すべきところは、胃の粘膜の再生や、胃潰瘍の治癒に効果があるビタミンUやビタミンKを豊富に含んでいるところです。また、ビタミンCの含有量も淡色野菜の中ではトップクラスという優秀さです。
このため、胃の痛みや胃腸の潰瘍に一定の効果があることがわかり、薬膳としてもにわかに注目を集めるようになりました。キャベツから発見されたビタミンUは別名キャベジンとも呼ばれており、胃腸薬としても知られています。胃腸の他にも、糖尿病や便秘、吹き出物、泌尿器系の疾患に薬効があるとされており、止血や痛み止めの効果も期待できると言われています。また、ガンの発生を抑える効果があるとも言われています。
キャベツの薬膳的利用法

胃の痛み、不快感にキャベツを
キャベツに含まれるビタミンUは胃の粘膜や胃壁を保護する働きをする栄養です。こちらは、熱に弱い成分なので、ビタミンUを意識して摂取する場合は、生で食べるか、さっと湯通しした程度のものを使用するのがいいでしょう。
キャベツジュースで体質改善
新鮮なキャベツのジュースを作り、1回250ミリリットルずつ温めてから食前に飲みます。10日間続けると胃・十二指腸の調子を整えるのに非常に効果的です。キャベツ75パーセント、セロリ25パーセントの割合のジュースでさらに良い結果が出たという例もあるそうです。胃壁の修繕を行ってくれるので、胃腸炎や胃潰瘍の方にもおすすめです。

煮たキャベツでガン予防
煮たキャベツを食べ続けることで、ガン予防につながると言われています。キャベツは煮すぎないことがポイントです。煮汁も捨てずに一緒にいただくと効能が高まります。
冷え性の人は生で食べ過ぎない
ビタミンUやビタミンCなどを効率よく摂取するためには、生食がオススメと紹介しましたが、生のキャベツには体を冷やす性質があります。冷え性の人は食べ過ぎないように注意しましょう。
キャベツを使った絶品の薬膳料理に挑戦

「キャベツと牛肉のワイン蒸し」
材料(2人分)
キャベツ 中1/2個
しゃぶしゃぶ用薄切り 牛肉 100グラム
セロリ 1本
ニンニク 1カケ
ローリエ、オールスパイス 適量
白ワイン カップ1/2
水 カップ1
塩・胡椒・レモン汁 各少々
刻みパセリ 少々
作り方
1.キャベツは2つ切りにして、芯はそぎ切り、葉は食べやすい大きさに切り分けます。
2.牛肉は5センチほどの大きさに揃えましょう。
3.セロリは食べやすく薄切りにして、ニンニクも薄切りにします。
4.ホウロウの鍋に、キャベツ、牛肉、セロリ、ニンニク、ローリエの順番で重ねて、オールスパイスを少々振りかけます。これを2、3回繰り返して、ミルフィーユ状に仕上げていきます。
5.分量の白ワインと水加えて、蓋をして30分ほど蒸し煮にします。
6.火が通り、全体が柔らかくなったら塩胡椒、レモン汁少々をかけて味をととのえてから器に盛り付け、刻みパセリを散らせば完成です。

薬膳の世界から見たキャベツについて紹介しました。キャベツは煮ても焼いても炒めてもおいしいのに、飲む薬と呼ばれているなんて、ぜひ日々の食卓に取り入れたいものです。お料理が完成した後に残るスープは、とても滋養があるものです。多くとれるようなら、食後の健康ドリンクとして飲んでもいいでしょう。お湯で薄めて胡椒をふりいれてから食べると香りが引き立って一層おいしく楽しめます。
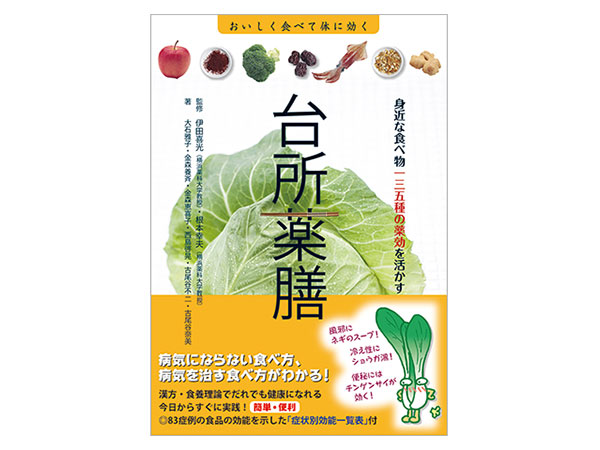
参考書籍:『台所薬膳 身近な食べ物135種の薬効を活かす』(万来社)

































