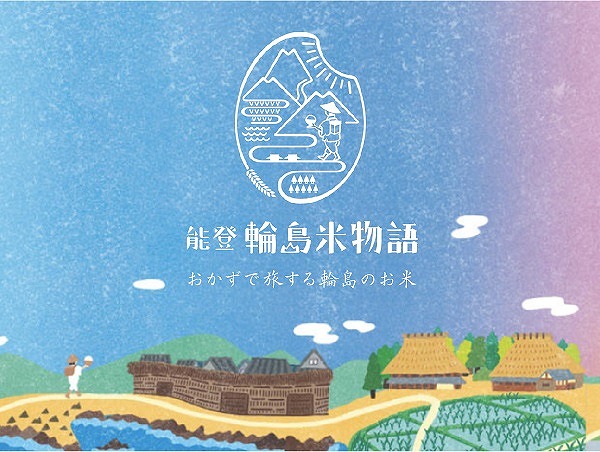お米屋は精米職人

昭和26年製の精米機。タンクには最大10俵(600キロ)のお米が入り、調整しながら精米すると3時間かかる
一般的な業務用精米機は、お米とお米を摺り合わせることでお米の皮を剥いていきます。ボタンを押すと一度に剥ける「ワンパス」と呼ばれるものが主流です。一方で、隅田屋商店の古式精米は、一度に精米せず7〜10回にわけて少しずつお米の皮を剥いていく「循環式」です。業務用精米に比べて、品質劣化に影響するお米の温度上昇も緩やか。当然、循環式のほうが時間がかかる上、技術が必要となってくると片山さんは言います。
「お米によっては、収穫したての秋と、半年以上経過した夏とでは水分量が変わります。すると、お米の弾力も変化するため、精米時にかける圧力も変わります。たとえば、収穫したての秋の圧力で精米すると、夏には同じ圧力ではお米の皮が剥けなくなってしまうのです。逆に、夏に調整した圧力のままで収穫したての秋のお米を精米すると、お米が割れてしまうこともあります。そのため、手動で微調整する必要があるのです」
さらに、驚くのが精米完了の見極めは「音」と「香り」だということ。
「もちろん色も見ますが。たとえば香りだったら、最初は玄米の香りですが、精米を始めると、その香りが少し抜けてきて、次第にお米の最もいい香りがしてきて、それが少し抜けてきたら完成です」。片山さんの話を聞いていると、本来のお米屋は精米職人であったことに気づかされます。
しかしながら、「お米をおいしく食べたい」という人にとって、「おいしいお米を選ぶ」ことや「おいしく炊飯する」ことは重視されていますが、精米にはなかなか目が向けられていないのが現実。銘柄や産地や価格でお米を選ぶのが一般的となっていますが、片山さんは古式精米を「お米の選択肢の一つにしてもらえれば」と言います。
それにしても、日本人はなぜ白米の白さにこだわるのでしょうか。精米機の中には、「上白米」など白米よりもさらに白いお米に精米できるものもあります。多くの日本人が無意識に抱いている“白米神話”を検証します。
【関連記事】「米屋の“とらや”になりたい」隅田屋商店【後編】