私たちは「味」をどこで判断している?
私たちの舌には味蕾(みらい)という組織があり、ここで甘味、塩味、苦味、酸味、うま味を受容しています。しかし、私たちが食べものを「おいしい」と感じるのは、味覚だけではないと笹野高嗣さんは言います。
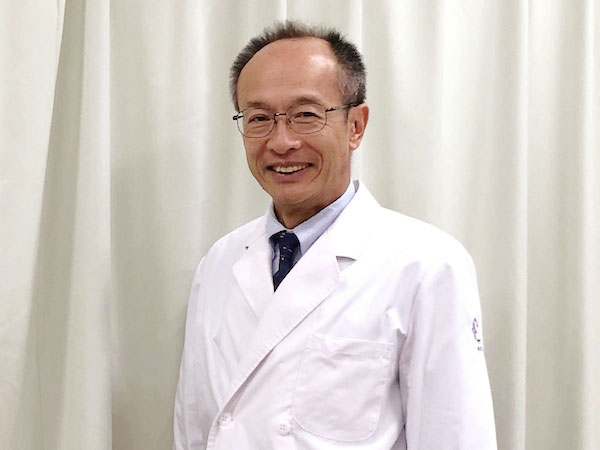
笹野高嗣さんプロフィール
東北大学名誉教授(口腔診断学)、医療法人徳真会顧問。
東北大学歯学部附属病院長、東北大学大学院歯学部長、東北大学大学院歯学研究科長、日本口腔診断学会理事長などを歴任。
「味覚は脳が感じる総合感覚です」と笹野さん。嗅覚、視覚、触覚など他のさまざまな感覚が統合されて生じる総合的な感覚だと言います。「『味は味蕾が感じる』のではなく、『味は味蕾が受容し脳が感じる』のです。そのため、香りやテクスチャー(硬軟や粘度など)、温度、色、ツヤ、形状、音、さらには、口腔状態、内臓の調子、雰囲気、気温、また食事をする際の気分や感情、過去の記憶、先入観などによっても味覚は変化します」(笹野さん)
たとえば、蕎麦(そば)は箸でつまんで「ずずっ」と音をたてて食べるとおいしいのに、パスタのようにフォークに巻いて食べるとおいしく感じない。ポテトチップスは「パリパリ」と自分の咀嚼(そしゃく)音を聞きながら食べるとおいしいのに、咀嚼音が聞こえないほど大音量の音楽をヘッドホンで聞きながら食べるとおいしさが半減する。キンキンに冷えたビールを紙コップに入れて飲んでもおいしくない。紙皿にぐちゃぐちゃに盛った料理は、陶器に丁寧に盛った料理と味は同じはずなのにどうも味がいまひとつ。駅弁は電車で車窓の景色を眺めて食べるとおいしいのに、自宅で食べるとおいしさが半減する。何気なく飲んでいたワインが1本2万円と知り、たちまちおいしくなった……。こうした感覚はすべて味覚が総合感覚であるがゆえなのです。

ビールの色、グラスの手触りや温度や質感、グラス同士が触れ合う音なども「おいしさ」の要素
学習の積み重ねが味覚を変える
では、味覚の役割とは一体なんなのでしょうか。笹野さんによると、「味覚とは食べられるものと食べられないものを区分けする本能的な機能」。たとえば、苦味は毒物のシグナルで、酸味は腐敗物のシグナルなので動物は絶対に食べないと言います。
「動物や赤ちゃんは苦味や酸味のあるものは食べません。子どものうちはコーヒーを飲みませんが、年頃になってくると体に取り入れても大丈夫だということが分かり、たとえばコーヒーを飲んだ後は少し気分が落ち着くと感じるようになります。そうした学習が積み重なってコーヒーを飲みたいと思うようになるのです。ビールや山菜の苦味なども同様です」(笹野さん)

子どもはコーヒーを飲まない
逆に、あるものを食べたり飲んだりしてお腹を壊した場合、その食べものや飲み物の味を「いやな味」と認識して、その味を避けるようになるそうです。私たちは食体験から得た学習によって、味覚を変化させています。だからこそ、食べものの嗜好(しこう)は人それぞれになる……というわけです。
味覚を訓練すれば誰でもソムリエになれる?
ところで、シェフやワインソムリエなどは、なぜ味覚が繊細なのでしょうか? たとえば、同じ条件でワインを飲み比べたときにワインごとの微妙な差異を認識できるのは、味覚の感受性が強いということなのでしょうか? この疑問に対して、笹野さんは「味覚の感受性の違いは多少はあっても、大きな差異はありません」と断言します。
「これも学習です。ワインソムリエは一般の人が識別できないようなわずかな味の差異を学習していく。学習していくから微妙な味の違いが分かるのです。才能もあるかもしれませんが、感覚を訓練しさえすれば誰でもできることで、後天的な要素が強いと言えます。日常の食卓でも濃い味ばかり食べているとその味に順応して薄い味がわからなくなり、逆に薄い味を食べ続けると薄い味も感じるようになります」(笹野さん)
笹野さんによると、東北大学の研究調査でタイ人と日本人の味覚検査をしたところ、辛い料理を好むタイ人は料理の味が濃くないと味を感じず、ダシの文化がある日本人は繊細なうま味を感じることが分かったそうです。

タイの辛い料理。食べると口の中が痛い
つまり、味覚には、私たちの毎日の食卓の連続が反映されているのです。糖度の高い野菜や果物が好まれているのも、砂糖が貴重だった昔に比べ、現代の私たちの食生活が豊かになったことを象徴する嗜好の変化だと笹野さんは見ています。
楽しく食事をするとおいしいものが増える
笹野さんは味覚を感じられなくなる「味覚障害」の治療を行っています。近年では「何を食べてもおいしくない」「味がわからない」と言って診察に訪れる高齢者が多いそうですが、味覚検査をすると異常がない場合もあるそうです。
「患者さんの話をよく聞かないと、味覚障害かどうかは分かりません。聞いていくうちに、『夜眠れない』『不安がある』『ひとりぼっちでさみしい』と打ち明ける患者さんもいます。それがおいしく食事ができない原因ですから、そちらから改善していく必要があります。味覚障害の治療は生活習慣まで入っていかないと治療できません。私たちは味覚だけでおいしさを感じているわけではないのです」
「食育」とは、「さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間を育てること」と農林水産省は定義していますが、笹野さんは「家族や友人たちと談話しながら楽しく食べることも食育」と指摘しています。総合感覚である味覚は、学習の積み重ねや生活習慣によって形成されていくことを思うと、子どものうちから楽しく食事をすることが「おいしい」ものを増やしていくことにつながると言えそうです。
【関連記事はこちら!】
子どもの好き嫌いは「偏食」ではない【前編】
ワンランク上の農業へ!役立つ資格の取り方、使い方 ~食育アドバイザー~
農業での生かし方いろいろ! 「野菜ソムリエ」ってどんな資格?




























