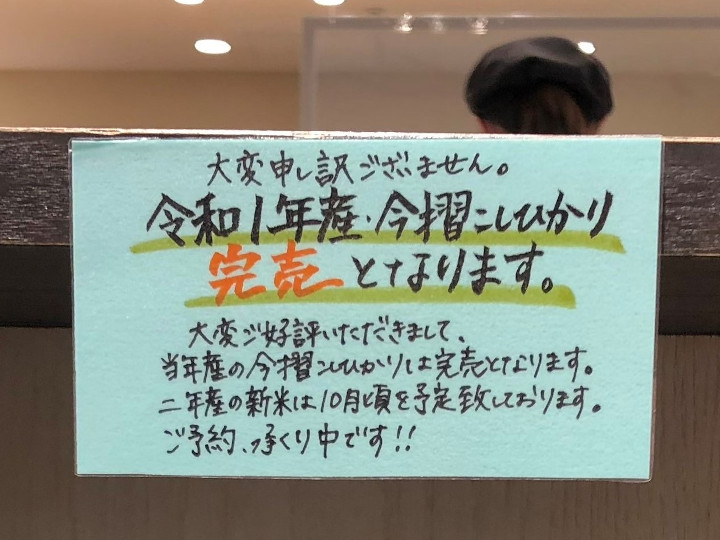珍しい野菜で飲食店中心の販路、コロナ禍でも売り上げ回復
さいたまヨーロッパ野菜研究会(以下「ヨロ研」)は発足が2013年。さいたま市の外郭団体とシェフ、若手農家などがチームを作り、地元で育てた野菜を使った料理でレストランや生産者を盛り上げるために活動をスタートさせた。
チームの発足に際し、シェフが農家に栽培を求めたのは、イタリア料理やフランス料理などで使われているが日本にはまだ定着していない珍しい野菜。地元の種苗会社が種を提供し、栽培方法を指導した。
課題は売り先となる飲食店の開拓。当初はレストランが見たことのない野菜の調理の仕方に戸惑い、販売量が増えなかった。だが新たなメニューを開発するレストランなどが登場し、メディアにも取り上げられたことで売り先が拡大。販路のレストランは埼玉県内を中心に約1200店まで増えた。

さいたまヨーロッパ野菜研究会の農家がつくったさまざまな野菜
そこをコロナが直撃した。レストランを中心に販路を増やしてきただけに、影響を免れることはできなかった。森田さんは混乱が最も大きかった時期のことを「4月は飲食店がどんどん休業していった」とふり返る。ヨロ研に参加している13人の農家の4月の売り上げは前年比で半減した。これが影響のピーク。
5月は前年比7割に戻し、6月は同9割まで回復した。飲食店が徐々に営業を再開したこともあるが、大きかったのは食品宅配のオイシックス・ラ・大地も販路に持っていたことだ。休校や在宅勤務により家庭で調理する機会が増えたことで、宅配の需要が急増。レストラン向けの販売が減った分をカバーし、売り上げをほぼ前年並みに戻すのに貢献した。
4月が野菜の端境期だったことも影響を小さくした。4月の売上高は、例年でも6月の半分くらいしかない。もし4月ではなく、6月に緊急事態宣言が出ていたら、打撃ははるかに大きくなっていただろう。

コロナの影響について語る森田剛史さん
販売の頼みはシェフの腕、信頼関係が生んだ取り組みとは
インタビューがここで終わっていたら、「コロナで減った飲食店向け販売を宅配でカバー」という内容の記事になっていたかもしれない。だが筆者の理解がそういった単純なものにとどまるのを防ぐため、森田さんはコロナによる混乱の中で自らが感じたことを丁寧に説明してくれた。