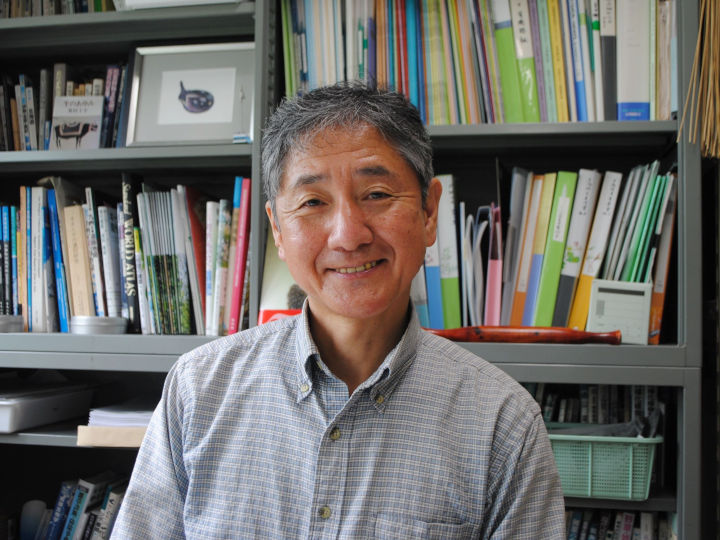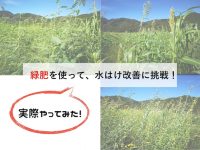緑肥とは
■露﨑浩さんプロフィール
 |
秋田県立大学生物資源科学部アグリビジネス学科教授。学術博士(1988年、岡山大学)。1989年、秋田県立農業短期大学(現・秋田県立大学)講師となる。2011年より現職。畑作物と雑草の生態に詳しい。雑草は防除だけでなく、活用の方法も探っている。趣味は水彩画で、雑草の絵もよく描く。 |
──緑肥について教えて下さい。
緑肥とは、栽培した作物を収穫せず、そのまま田畑にすき込んで、次期作の肥料にすることを言います。土壌や太陽光など、その土地にある資源をうまく活用することができます。
日本は農作物を作るための燃料といったエネルギーや化学肥料のほとんどを輸入に頼っています。農薬の原体(有効成分を製品化したもの)にしても、かなりの割合を輸入しているはずです。このような輸入に依存する状況を徐々に改める必要があり、日本の中、あるいは地域の中で資源を活用し物質の循環ができるような農業を志向していかなければならないでしょう。
そのための手段の一つが緑肥です。緑肥は太陽を浴び、土壌中の養水分を吸収して育つので、地域の中で物質が循環する上で非常に重要だと考えています。肥料としての利用に加えて、さまざまな効果があるんですよ。
地面を覆って雑草を抑える
──緑肥は、農地に養分を補うイメージが強いです。ほかに、雑草を抑制する効果も期待できるそうですね。
はい。雑草の抑制には、主に四つの方法があります。一つ目は、草刈り機や除草ロボットを使う「機械的制御」。二つ目は、除草剤を使う「化学的制御」。三つ目は、アイガモ農法のような「生物的制御」。そして四つ目が「耕種的制御」です。田畑の輪作体系の中に緑肥を組み込んで次期作での雑草の発生を抑えるのは、この耕種的制御に当たります。
比較的生育の早い緑肥を育て、地面を覆って光を遮れば、雑草の発芽や生育を抑えることができます。こうした緑肥は「カバークロップ」とも呼ばれます。カバークロップの中には、作物の栽培中も生えた状態にする「リビングマルチ」もあります。たとえば、大豆の畝の間に秋まきの大麦をまくと、大麦は畝間の雑草を抑えます。その後、大麦は夏場の暑さで枯れてしまうんです。
土づくりに養分補給、土壌病害の軽減など八面六臂(ろっぴ)の活躍ぶり
──雑草の抑制以外に、緑肥にはどんな効果がありますか?
まず、土づくりの効果です。緑肥を栽培すれば、作土(作物の根が張る土壌の表層部分)に有機物が供給されます。深くまで根を張る緑肥も多いので、根が到達することで、深い土層の土壌改良効果も期待できます。耕盤と呼ばれる硬い層が軟らかくなったり、水はけや保水性が高まったりする効果もあります。
次に、減肥の効果です。ヘアリーベッチといったマメ科の緑肥は、根に共生している根粒菌が空気中の窒素をアンモニアに変えます。ヘアリーベッチをすき込むと、その窒素が次の作物に養分として活用されます。マメ科は窒素とカリの養分濃度が高い、ソルガムなどのイネ科はカリの養分濃度が高いというように、種類によって効果は変わります。一つの緑肥だけで養分を賄うのではなく、足りない養分は別の方法で補うのが基本です。

ヘアリーベッチ
ほかに、輪作作物が増えることで、土壌病害の軽減にもつながります。有害センチュウの防除も緑肥に期待される効果の一つです。マリーゴールドや燕麦(えんばく)などが防除効果を持ちます。
過剰な養分を吸わせるという使い方もあります。ヒマワリなどがそうで「クリーニングクロップ」と呼ばれるんです。ハウスの中の土壌は養分が過剰になりがちで、作物が吸いきれずにたまった塩類を緑肥に吸収させるのです。そして、その緑肥はハウスの外に持ち出します。
緑肥を実践する前にすべきこと
──緑肥を実際に使おうと思ったら、どうすればいいでしょう?
「緑肥利用マニュアル」が農研機構のウェブページで公開されており、緑肥の種類ごとに使い方や事例を紹介しています。一気に大面積でドンと導入するのではなく、まずは狭い面積で試行することが必要だと考えます。もし近場で先行的に緑肥を活用している農家がいれば、実際にどうなっているか見せてもらってから取り入れるのがよいでしょう。
私たちのキャンパスがある大潟村では、農家が複数の緑肥を選んで、まずは畦畔(けいはん)で植えて生育の良いものを選抜していきました。最終的に、ヘアリーベッチが良いということで、複数の農家が緑肥として使い、ほかの地域にも広がっています。
緑肥の課題の一つが、種子の価格が高いことです。種子を購入すると、どのくらいの量をまくかが袋に書かれていて、ヘアリーベッチだと10アール当たり3~5キロとされています。3キロでいいのか、それとも5キロ必要なのか、それによって費用が大きく変わってきます。
私たちが調べたところ、圃場(ほじょう)の排水性が良ければ3キロで足りると分かりました。輪作の中にヘアリーベッチを組み込むなら、事前に圃場の排水性を良くするよう工夫し、その後にまけば、種子代を抑えられるわけです。

秋田県立大学の圃場の一画では、小麦と大豆、緑肥のヒマワリとヘアリーベッチの輪作をしている
タイミングが大切
──緑肥を使う上での注意点はありますか。
すき込むタイミングと、すき込んでから種子をまくまでの期間が大切で、皆さんが悩むところだとも思うんです。緑肥が圃場にすき込まれると、土壌中の菌類や細菌といった微生物が「エサがたくさん来た!」と喜んで食べて、自分の体の養分にして使っていくわけです。最初に窒素が微生物の体に取り込まれるので、そのタイミングで作物を植えてしまうと、作物が必要とする窒素が足りなくなることがあります。
そのため、一般的に緑肥をすき込んでから植え付けるまで1カ月以上時間を置きましょうと言われています。比較的スムーズに分解が進むので、そんなに待たなくていい種類の緑肥もあります。
では、緑肥がどの程度育ってからすき込むのがいいか。これも一般論として、開花期とか、イネ科の作物であれば穂が出る出穂(しゅっすい)期がちょうど良いとされています。比較的軟らかいので、土の中にすき込まれてから分解が速く進みます。それより後になると、分解が非常に遅くなることがあります。逆に前だと生育量が少なく、土壌の物理性を改善するなどの緑肥の効果が十分得られなくなりかねません。
それから、すき込みには特殊な機械が必要な場合が多いです。
機械への初期投資がネック
──農家がよく使うロータリー(田畑をおこす機械)くらいじゃ足りないのでしょうか?
丈が高かったり繁茂していたりすると対応できません。よく使われるのが、緑肥を細断できるフレールモアです。イネ科のソルゴー(ソルガム)は2メートルくらいと、かなりの背丈になりますから「とりあえず植えて育ったけど、どうしましょう」となってしまったという話も聞きます。ヘアリーベッチも、60~70センチくらいの丈にわさっと生い茂りますね。
フレールモアだと刈りながら細断できるのですが、それなりの価格がするという点は、緑肥を導入する上でのネックの一つです。

生育が進むと草丈が2メートルを超えるソルゴー
なお、農林水産省の「環境保全型農業直接支払交付金」では、カバークロップやリビングマルチ、草生栽培(果樹園の下草を除草せず生やした状態で栽培すること)といった緑肥や緑肥に似た効果を持つ栽培方法に交付金を出し、支援しています。
緑肥利用マニュアル -土づくりと減肥を目指して-(農研機構)