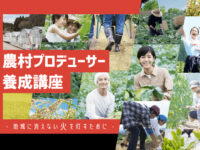コロナで飲食店向けの売り上げは7割減、宅配セットの需要が増加
とても有名な生産者なので、プロフィールの紹介はごく簡単なものにとどめたいと思う。帝人を退職し、土浦市で就農したのが1999年。現在の栽培面積は約6ヘクタールと、野菜の有機農家としては大規模の部類に入る。
久松さんの存在を際立たせているのは、たくさんの品目を安定して育てる技術に加え、SNS(交流サイト)などを使った発信力だ。「キレイゴトぬきの農業論」(新潮新書)などの著書を通して有機農業の意義や営農戦略について理詰めで解説し、若手農家を中心に幅広く支持を集めている。
農業界へのコロナの影響は、消費者が食事をする場所の変化を反映してすでに明暗がはっきりしている。「巣ごもり消費」の一環で家での食事が増える一方、飲食店で食べる機会は減った。久松さんの場合、影響はともにあった。個人向けの宅配と飲食店という二つの販路を持っているからだ。

飲食店向けに出荷する野菜
飲食店向けは、2020年3月のはじめごろから落ち込み始めた。「宴会がキャンセルになった」などの理由で注文がストップすることが増え、常連客に支えられるような小さな店にも影響が及び、3月末には注文がほぼゼロになった。
その後、状況に多少の変化はあったが、本格的な回復の糸口はつかめないまま1年が過ぎた。コロナ前は毎週安定して10~15店から注文があったが、いまは1~3店がせいぜい。営業を縮小するだけでなく、閉店した売り先もあった。2020年の飲食店向けの売り上げは、前年比で7割減った。
これに対し、個人向けの宅配セットは需要が急増した。久松さんはコロナ前、宅配セットの市場の拡大について懐疑的に見ていた。共働き世帯が増えたことで、家でゆっくり調理する時間的な余裕がある人が減ってきたからだ。だが、コロナでいい意味で予想が外れ、売り上げは4割増えた。
飲食店向けの減少と個人向けの増加を相殺すると、全体では1割の増加になった。伸び率は個人向け宅配のほうが小さいが、販売量はもともと飲食店向けより多かったので、コロナ禍のもとでも売り上げを増やすことができた。

出荷作業をしているスタッフと
新規顧客が増えた理由とは
個人向けの販売が増えた要因を詳しく見てみよう。