お米に対する先入観を打ち壊す
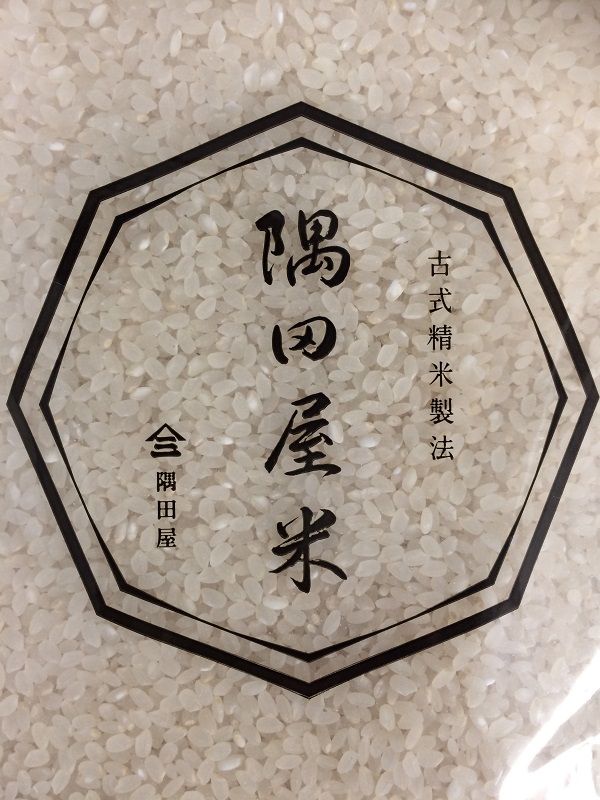
とらやの羊羹のように、加工(精米やブレンド)で差別化を図った隅田屋商店の「隅田屋米」
炊飯前はうっすらと黄みがかった隅田屋商店のお米は、炊飯すると生米のときよりも白くなります。
しかしながら、片山さんによると、経時劣化が早いそうです。
「炊飯器に入れたまま数時間置いておくと、工業用精米機の一般的なお米は4時間ほどすると劣化が始まり黄色くなりますが、うちのお米は2時間くらい。お米の表面に残った旨み成分が黄色くなってかたくなってしまうのです」(片山さん)
一方で、旨み成分を取ってしまって真っ白にしてしまえば、ごはんは悪くなりにくく、虫の発生率も低くなると言います。
それでも、隅田屋商店のお米を選ぶ人たちがいるのは、その味わいに惚れ込んでいるから。香り高さや味わい深さを取るか、見た目や扱いやすさを取るか。その選択は消費者に委ねられています。
片山さんが隅田屋商店のお米を「古式精米製法飴色仕上げ」というふうに、「黄色」ではなく「飴色」と表現すると、たちまち魅力的に聞こえるから不思議。なぜ黄色いかを理解したつもりでも、「黄みがかったお米」に対するネガティヴなイメージが少なからずあったことに気づかされました。
「日本ではお米が白くない時代が長かったため、DNAに白への憧れがインプットされてしまっているのです」と片山さんは言います。そして、「白は宗教的・思想的につくられた色」と言うのは、農学者の佐藤洋一郎さん。現代では白米は「白米」と書きますが、かつては「燦米」と書いて「はくまい」と読んでいたそうです。“燦然たる米”。白米への憧れがどれほど強かったかを思わせる表現です。
私たちは無意識のうちにお米に対してさまざまな思い込みがあるようです。その理由を片山さんは「主食だから」と言います。つまり、あって当たり前の日常食だからこそ、イメージだけで判断してしまい、実はお米に対して知らないことだらけという状況に陥っているのです。
「お米に対する先入観を打ち壊したい。お米の選択肢を広げたい」と片山さん。隅田屋商店の古式精米は、お米に対する価値観に一石を投じています。
【関連記事】「米屋の“とらや”になりたい」隅田屋商店【前編】




























