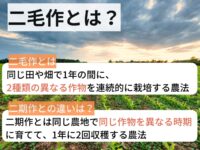転作(てんさく)の定義とは?
転作とは、これまでと違う作物を同じ農地で育てることを指します。例えば、何年も米を作ってきた田んぼで、大豆や麦、野菜など別の作物を栽培するようなケースが代表的です。

この転作という言葉には、実は2つの意味があります。1つ目の意味では、例えば将来的にまた米を作るつもりで、一時的に別の作物を育てるようなケースも含まれます。一方、その土地で何を作るかを根本的に変えること、つまり再び元の作物に戻す予定が無い場合も転作に入ります。
こうした転作が行われた土地は転作地、特に水田を転用した場合には転作田と呼ばれます。水田の多い地域では、農地の使い方を見直す手段として、転作が重要な選択肢となっています。
転作の例
転作の代表的な例としては、稲作から花卉(かき)栽培に切り替えるケースや、大豆・小麦などの畑作物に変更するケースが挙げられます。最近ではトウモロコシ栽培への転換を進める事例も増えてきました。いずれも、水田の有効活用や収益性の向上を目的に行われています。
転作を行う理由
近年、米の消費量は年々減少しており、生産される米が余る傾向にあります。こうした背景を受けて、国は米の生産量を調整するために減反政策を導入しました。
しかし、田んぼを空けていると、その分農家の収入は落ち込んでしまいます。そのため別の作物を栽培する転作を選ぶ農家が増えています。
転作と輪作・二毛作の違い
転作は、農地の活用方法を変える手段のひとつとして広く知られていますが、実はよく似た言葉に輪作や二毛作といったものがあります。それぞれの意味や目的には違いがあり、混同されやすい点でもあります。
どのような点が異なるのか、解説していきます。
転作と輪作の違い
輪作は、同じ土地で複数の種類の作物を数年単位で順番に栽培する方法で、連作障害を防ぐことが主な目的です。
また、同じ作物を連続して育てることを単作、ひとつの畝で複数の作物を同時に育てるのが混作、畝ごとに異なる作物を並行して育てるのが間作と呼ばれています。
転作と二毛作の違い
二毛作とは、1年のうちに同じ農地で2種類の異なる作物を育てる方法です。季節の特性を活かして、例えば夏に米を作った後、冬の間に麦や菜種、ジャガイモなどを裏作として栽培することが挙げられます。
転作のメリット
転作には、単に作物を変えるというだけでなく、農業経営にとってさまざまなメリットがあります。特に連作障害の軽減や土壌環境の改善、更には制度による経済的な支援といった点で、農地の持続的な活用に役立つ手段として注目されています。
一体どのようなメリットがあるのか、それぞれ解説していきます。
連作障害が軽減する
同じ作物をずっと同じ土地で作り続けていると、土の中に病気のもとになる菌や害虫がたまりやすくなり、作物の育ちが悪くなる連作障害が起こることがあります。
そこで、水田として使われていた土地を再び水で満たしてしばらく湛水(たんすい)状態にすると、空気が少ない環境になるため、多くの病原菌が生きていけなくなります。これによって、連作障害を防ぐ効果が期待できます。
ただし、中にはその環境でも生き延びてしまう菌もいるので、万全とは言い切れません。状況に応じて、作物の組み合わせや管理方法を工夫することが大切です。
土壌環境が改善する
水田を畑に切り替えると、土がしっかり乾くようになり、深いところまで空気が届くようになります。これによって土の中で微生物の働きが活発になり、栄養の循環がスムーズになります。
また、水はけが良くなることで土の中に水がたまりにくくなり、作物の根がしっかりと地中深くまで伸びやすくなります。根が元気に育つことで、作物もより健康に育ちやすくなります。
更に、水田と畑では出てくる雑草の種類が異なるため、交互に使うことでお互いの雑草を抑える効果も期待できます。
補助金が支給される
転作を進めるに当たっては、国の支援制度も活用できます。条件を満たすことで転作田に対して補助金が支給される制度があります。例えば、麦や大豆を栽培する場合は、5年に1度は水を張る必要がありますが、そうした条件を守った上で栽培すると、10アール当たり3万5,000円の交付金を受け取ることができます。
転作のデメリット
転作には多くのメリットがある一方で、注意すべき点もあります。
思ったほど収量が上がらなかったり、土壌や作物に合わないケースが出てくることもありますし、畑から田んぼへ戻すときには、それなりの手間やコストも掛かります。どのようなデメリットがあるか、それぞれ解説していきます。
地力が低下する可能性がある
水田を畑に変えると、これまで水の中で保たれていた栄養分を作物がどんどん吸収していくため、少しずつ地力が落ちてしまうことがあります。そのまま栽培を続けていると、やがて収量が落ちる可能性もあるため注意が必要です。このようなときは、堆肥や緑肥、稲わらなどをすき込んで、土にしっかりと栄養を与えてあげることが大切です。
米の食味が低下する可能性がある
畑に転換していた土地を再び田んぼに戻すと、土壌中の窒素が過剰になり、米に含まれるタンパク質が増えることで、食味が落ちることがあります。特に転作から復田の初期には、この傾向が見られやすいため、肥料の与え方や栽培管理には注意が必要です。
復田の労力及びコストが大きい
水田から畑への転換は比較的簡単に行えますが、畑から水田に戻す復田には多くの手間が掛かります。水の管理や排水設備の再整備が必要になることもあり、作業量も増えるため、労力と費用の両面で負担が大きくなりがちです。また、転作のサイクルが短くなるほど、この負担は繰り返し発生するため、コストの増加にもつながります。
転作に適している農地の特徴
転作に向いているのは、乾田型と呼ばれるタイプの水田です。乾田型の土壌は透水性が高く、水はけが良いため、排水さえしっかりできれば畑としても使いやすくなります。
転作に適した作物と栽培方法
実際に転作を行う際には、どの作物を選ぶかがとても重要です。水田から転換した土地でも育てやすい作物を選ぶことで、栽培の失敗を減らし、安定した収穫につながります。
ここでは、転作に適しているとされる代表的な作物をいくつか紹介し、それぞれの特徴や栽培のポイントについても触れていきます。
大豆
大豆は水田転作の作物として非常に人気があり、広く栽培されています。ただし湿害に弱いため、排水対策はしっかり行う必要があります。畑にした際は水はけの良い状態を保ち、明渠(めいきょ)や暗渠(あんきょ)などで排水路を整えると安心です。
また、大豆の根には根粒菌が共生しており、土の状態が良ければ自ら空気中の窒素を取り込んで育ちます。地力が不安な場合は堆肥を入れておくと、より安定した生育が見込めます。
小麦
小麦も大豆と同様、水田からの転作作物として多くの地域で栽培されています。湿害に弱いため、排水性の高い圃(ほ)場作りが基本です。水はけを良くしておくことで、発芽不良や根腐れを防ぐことができます。
土壌はpH6.0前後が適しており、必要に応じて苦土石灰などで調整すると良いでしょう。堆肥や稲わらをすき込んで地力を高めておくと、より安定した生育が期待できます。
トウモロコシ
トウモロコシは、水田転作先として注目されている作物のひとつです。特に子実用トウモロコシは家畜の飼料として需要が高く、近年では国内生産の拡大が進んでいます。
栽培時は排水対策に注意しましょう。圃場の水はけを良くすることで、湿害による根腐れや発芽不良を防ぐことができます。
アスパラガス
アスパラガスは多年草の作物で、一度植えると10年以上にわたり収穫が見込めます。水を多く必要とするため、水田からの転作にも適しています。
また、アスパラガスはデリケートな作物で、風やゴミで曲がったり、病気にもかかりやすいため、日ごろの観察と防除作業も大切です。堆肥を入れて地力を高めたり、マルチを活用することで雑草の抑制や土壌の保湿にもつながります。
ナス
ナスも水田からの転作作物として適しており、湿った環境を好むため、もともと水田だった土地でも栽培しやすい作物のひとつです。ただし、過湿による根腐れや病気を防ぐためには排水対策が不可欠です。また、ナスは連作障害を起こしやすい作物でもあるため、ナス科以外との輪作を取り入れるとより効果的です。
ジャガイモ・サトイモ
ジャガイモは湿気に弱いため、排水性の高い圃場が必要です。高畝を作る、あるいは暗渠排水を設けるなどして、水はけの良い環境を整えると安心です。また、ネギなどとの輪作を取り入れることで、連作障害の軽減にもつながります。
一方、サトイモは湿った環境を好むため、もともと水田だった場所でも比較的栽培しやすい作物です。乾燥しやすい夏場にはしっかりと灌水することが収量アップのポイントになります。
転作に活用できる「水活交付金(転作奨励金)」とは?
水田を有効活用するための支援制度として、国が実施しているのが「水田活用の直接支払交付金(通称:水活交付金)」です。麦や大豆、飼料用米などの作物を水田で栽培する農業者に対し、一定の条件を満たせば交付金が支給されます。
令和4年度からは交付対象となる水田の条件が見直され、今後は5年間全く水稲を作らない田んぼは、対象外となる方針が示されています。
水活交付金(転作奨励金)の交付額
作物の種類によって交付金額は異なります。例えば、麦や大豆、飼料作物の場合は、10アール当たり3万5,000円の交付を受けることができます。
この他にも、対象作物によって交付単価が設定されており、戦略作物助成では10アール当たり2万円〜10万5,000円、産地交付金では10アール当たり1万2,000円〜10万5,000円といった幅があります。作付け品目や用途によって支援内容が変わる点に注意が必要です。
農業経営の安定と発展の選択肢に

転作は、農地の有効活用や収益性の向上、更には連作障害の予防や土壌改善といったさまざまなメリットをもたらしてくれる方法です。特に水田が多い地域では、こうした取り組みを通じて、農業経営の安定や地域農業の持続的な発展が期待されています。
もちろん、転作には地力の低下や復田の負担など、いくつかの注意点もありますが、作物選びや圃場管理を工夫することで、これらのリスクも抑えることができます。
水活交付金などを活用すれば、経済的な負担を軽減しながら取り組むことも可能です。農業の未来を見据え、環境や市場の変化に柔軟に対応する手段として、転作という選択肢を考えてみてはいかがでしょうか。